HEALTH
ふとしたときに、自分の体からいつもと違う“ニオイ”を感じたことはありませんか? もしかしたらそれは「疲労臭」かもしれません。疲労臭を改善するには、腸内環境を整えることが大切です。疲労臭の原因や日常生活に取り入れやすい対策方法を紹介します。
◆あわせて読みたい

疲労臭とは、過度の疲労やストレスの蓄積によって体内にアンモニアがたまり、それが呼気や皮膚ガスとして排出されることで生じるニオイのこと。ツンとしたアンモニア臭が特徴で、洗ってもすっきり落ちないケースも。
通常、アンモニアは肝臓で分解され、尿として体外へ排出されます。しかし何らかの要因によって肝臓の代謝機能が悪くなるとアンモニアの分解が追いつかず、血中のアンモニアが分解されずに残ることで、疲労臭へとつながるのです。
例えば、過度な飲酒や偏った食生活、血行不良などが肝臓の働きを弱め、疲労臭を引き起こすきっかけとなります。

自律神経が乱れて全身の代謝や血流調整がうまくいかなくなり、肝臓にも過度な負荷をかけてしまうことが疲労臭の原因の一つです。
自律神経は交感神経と副交感神経の2つからなり、両者がバランスをとりながら血圧や体温、消化吸収などの機能を調節しています。しかし、過度な疲労やストレス、睡眠不足、生活リズムの乱れが続くと、自律神経のバランスが崩れ、交感神経が優位な状態が続きます。
これにより肝臓への血液供給が滞り、肝細胞に酸素や栄養が十分に届かず機能低下を招いてしまいます。その結果、アンモニアの分解能力が落ちて血中のアンモニア濃度が高くなります。
さらに、交感神経が優位になると心拍数も増え、アンモニアを含んだ皮膚ガスが出やすくなることで、疲労臭が発生しやすくなります。
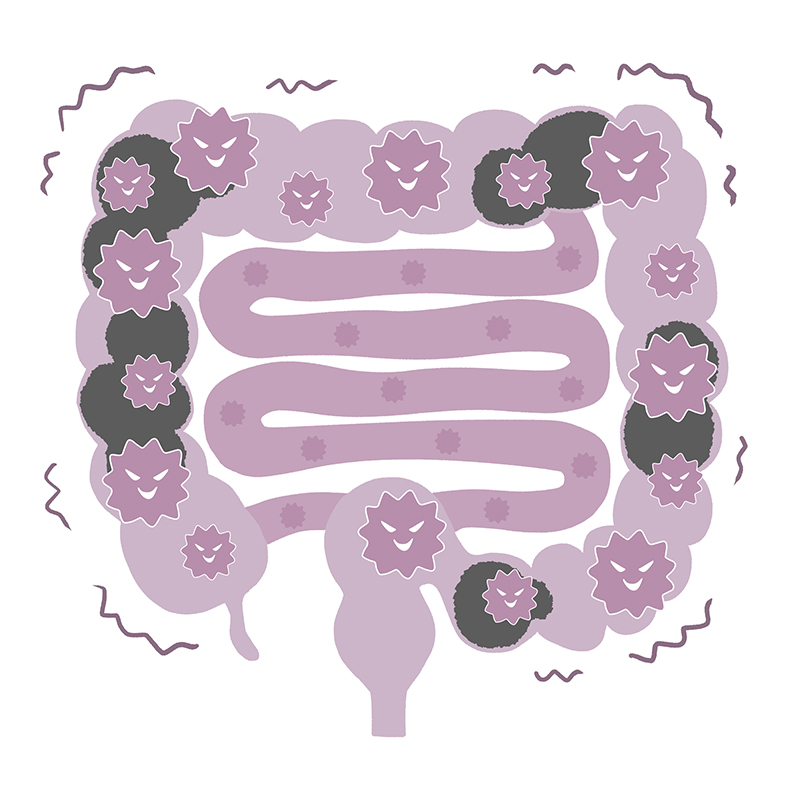
腸内環境が悪化して悪玉菌が増殖することも、疲労臭につながる原因として挙げられます。
腸内には数多くの腸内細菌が存在しており、大きく分けて善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3つに分類されます。
このうち、悪玉菌は体にとって良くない働きをする腸内細菌。腸内でアンモニアを作り出す働きがあり、腸内で発生したアンモニアが血中に流れることで疲労臭につながります。
特に、動物性タンパク質や脂質の多い食事、食物繊維不足、便秘の継続などが、悪玉菌を増やす要因として挙げられます。
疲労臭対策では、肝臓の負担を減らすとともに自律神経や腸内環境を整えることが大切。日常生活に取り入れやすい方法を紹介します。

疲労臭を軽減するには、肝臓に余計な負荷をかけない生活を心がけましょう。高タンパク・高脂肪の食事を控え、脂質の質を選ぶことがポイント。例えば、赤身肉を控え、脂の少ない魚や発酵食品、野菜を中心にとるようにしましょう。
また、疲労回復効果が期待できるクエン酸をとることも効果的。レモン、酢、梅干しなど酸味のある食材に含まれるため、調味料やご飯のお供などに取り入れてみてください。
運動は血行を促進して老廃物の排出を促すとともに、自律神経のバランスを整える効果が期待できます。また、運動で腰周りの筋肉を動かすことで、腸のぜん動運動が活発になり、便秘の改善につながります。
おすすめは、ウォーキングやジョギング、スイミング、ストレッチなどの有酸素運動です。通勤時に一駅分歩いたり、家事の合間に体を動かす「ながら運動」をしたりするのも効果的です。
なお激しい運動をするとアンモニアが汗として排出され、汗が臭くなる可能性が。運動で汗をたくさんかいた際には、汗をすぐに拭き取り、服を着替えるようにしましょう。
睡眠の質を整えて体を十分に休めることも効果的。体が休まっていないと、疲労が蓄積して自律神経も乱れやすくなります。自律神経は腸の働きにも関係しているため、自律神経の乱れによって腸内環境も悪化しやすくなります。
毎日同じ時間に就寝・起床するリズムを作る、寝る前のスマホ操作や明るい照明の使用を控えるなどの工夫をしましょう。睡眠リズムを整えると体がしっかりと休まり、自律神経を整えることにつながります。

腸内のビフィズス菌を増やすことも、疲労臭対策に効果的です。
ビフィズス菌は善玉菌の一種で、腸内で乳酸や酢酸を作り出す働きがあります。この乳酸や酢酸には、大腸を弱酸性にし、アンモニアを発生しにくくする環境を作る働きがあるのです。
腸内のビフィズス菌を増やすには、ビフィズス菌入りのヨーグルトなどを食べるのがおすすめ。ただし、食べ物からとった善玉菌は短期間で体外へ排出されるため、毎日継続して摂取する習慣を作りましょう。
さらに、腸内のビフィズス菌を育てるために、水溶性食物繊維やオリゴ糖を含む食材をとることも欠かせません。水溶性食物繊維は海藻類や豆類、オーツ麦などに多く含まれます。オリゴ糖はバナナや玉ねぎ、ごぼうなどに多く含まれるため、「味噌汁に海藻や玉ねぎなどを入れる」「朝食にバナナを食べる」など日々の食事に取り入れましょう。
生活習慣の見直しに加えて、腸内環境を整えるサプリメントを取り入れる方法もあります。サプリメントは飲むだけで不足しがちな栄養素をとれるため、忙しくて十分なセルフケアができない場合にも取り入れやすいのが特徴です。
サプリメントの中には、ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌を直接摂取できるものや、食物繊維などの善玉菌のエサとなる成分をとれるものがあります。サプリを選ぶ際には、自身の食生活と照らし合わせ、不足しがちな成分をとりましょう。
<参考文献>
※ 関根嘉香,木村桂大,梅澤和夫「皮膚ガス測定は何に役立つか?」

監修してくれたのは…医師・後藤利夫さん
1988年、東京大学医学部卒業。独自の無麻酔・無痛大腸内視鏡検査法「水浸法」を開発。大腸内視鏡6万件以上無事故のベテラン医師。大腸がん予防から始まった腸内細菌や乳酸菌にも造詣が深く、菌のパワーを使って健康になる方法を各所で伝授し続けている乳酸菌の専門家。サプリメント「今日から腸活!」の監修も務める。
編集/根橋明日美 写真・イラスト/PIXTAほか

2026年1月16日(金)23:59まで

2026年1月16日(金)23:59まで

2025年12月16日(火)23:59まで

2025年12月16日(火)23:59まで

2025年12月16日(火)23:59まで