HEALTH
「長寿菌」という言葉をご存じですか? 長寿菌は健康な人の腸に多く存在する善玉菌で、腸内環境を整え、不調を改善するカギになる存在です。健康的に年齢を重ねるために知っておきたい長寿菌の特徴や増やし方を紹介します。
◆あわせて読みたい

長寿菌とは、健康寿命が長い人の腸内に多く存在する善玉菌のこと。具体的には、ビフィズス菌、大便桿菌、ラクノスピラ(菌の総称)などが挙げられます。
これらの菌は、腸内で悪玉菌の増殖を抑える働きをしたり、酪酸や酢酸などの短鎖脂肪酸を作り出したりすることで、腸の働きをサポートしてくれます。短鎖脂肪酸は善玉菌が食物繊維などを分解する際につくられる代謝物で、腸の粘膜を保護したり免疫機能を高めたりする働きのある物質です。
実際に、奄美大島の健康長寿の100歳の女性の腸内を調査した研究では、彼女の腸内に含まれるビフィズス菌の量は、平均的な60~80歳の人のなんと30倍以上だったという報告もあります。
こうした研究結果を踏まえ、健康長寿の達成には、長寿菌が腸内細菌の40~60%を占めることが理想的だと考えられています。
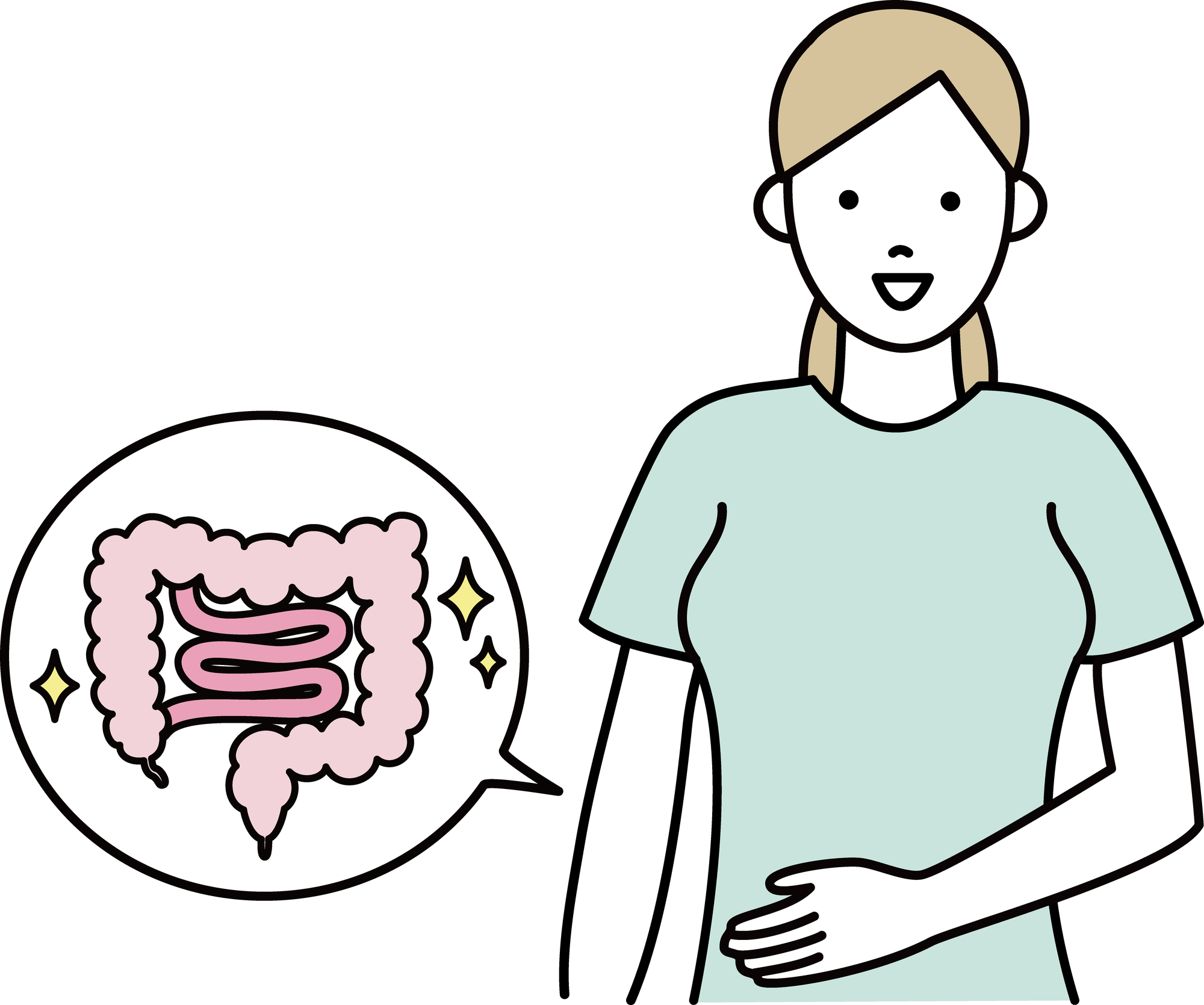
自分の腸に長寿菌がどのくらいいるのか、どうすればわかるのでしょうか? もっとも簡単にできる方法が便の状態を観察することです。
長寿菌が多い腸では、便は以下のような特徴が見られます。
・色は黄褐色〜茶色で自然なツヤがある
・形状はバナナのように滑らかで太さも均一
・あまり力まずスムーズに排便できる
・においが強すぎず不快感が少ない
逆に「便がコロコロと硬い」「色が黒っぽい」「便やおならのにおいがきつい」などの特徴がある場合は、腸内環境が乱れ、長寿菌が減っている可能性があります。
自分の腸がどんな状態にあるかを知る大切な手がかりとなるため、毎日排便の状態を確認しましょう。
長寿菌の数を増やすには、毎日の生活にちょっとした工夫を取り入れることが大切。今日から実践できる5つのアプローチを紹介します。

長寿菌の代表格ともいえるビフィズス菌は、ヨーグルトや乳酸菌飲料などの発酵乳製品に含まれています。これらの食品を摂ることで、直接的に腸内のビフィズス菌を増やしましょう。
ただし、食べ物から摂った菌はあくまでもお客様。腸内に定着しにくいため、毎日継続的に摂取することが大切です。「朝食にヨーグルトを取り入れる」「間食にドリンクタイプの乳酸菌飲料を選ぶ」など、ライフスタイルに合わせて無理なく取り入れましょう。
また、ビフィズス菌の働きを助けるオリゴ糖も一緒に摂ることで、菌の定着がより促進されます。玉ねぎやバナナ、大豆製品などのオリゴ糖を含む食材も積極的に摂りましょう。
善玉菌のエサとなる食物繊維を積極的に摂ることも、長寿菌を増やすことにつながります。特に意識して摂りたいのが「発酵性食物繊維」。発酵性食物繊維を善玉菌が分解・発酵することで短鎖脂肪酸が作られます。
発酵性食物繊維が豊富な食材には、海藻類、きのこ類、ごぼう、アスパラガス、大麦、にんにくなどがあります。例えば、ごぼうとわかめの味噌汁、きのこと大麦を使った炊き込みご飯などは、発酵性食物繊維を効率良く摂れるメニューといえるでしょう。
日々の食事にこれらの食材を少しずつ取り入れることで、長寿菌の活動を自然にサポートできます。

和食には味噌や醤油、納豆、ぬか漬けなどの発酵食品はもちろん、根菜や海藻などの食物繊維が豊富な食材を使った料理が多くあります。
例えば、味噌汁は1杯で善玉菌が豊富な発酵食品と食物繊維を同時に摂れる腸にやさしいメニューです。具材に大根やわかめ、豆腐などを組み合わせれば、さらに効果的。腸活において、和食はまさに理想的な食スタイルなのです。
また、和食中心の生活は、肉類などに多く含まれる動物性タンパク質や脂質の摂りすぎを自然と抑えることができ、腸内で悪玉菌が増えるのを防ぐことにもつながります。

適度に体を動かすことで、腸や腰回りの筋肉が刺激されて腸の蠕動運動が活性化し、便通の改善につながります。
特に、腰回りやお腹を動かすストレッチ、ウォーキング、ヨガなどの軽い運動がおすすめ。腰回りの筋肉を動かすことで、便を押し出す力を維持し、スムーズな排便につながります。
日常生活に「歩く時間を5分長くする」「寝る前に簡単なストレッチを取り入れる」といった小さなアクションを取り入れるだけでも、腰回りの筋力を維持しやすくなります。
忙しくて食事や運動を思うようにできないという場合は、サプリメントを上手に活用するのも一つの方法です。ビフィズス菌や食物繊維、オリゴ糖などが配合された腸活サプリを選ぶことで、効率的に腸にいい成分を摂取できます。
ただし、サプリメントはあくまでも補助的な存在。普段の食事や生活習慣を整えた上で、足りない分を補うというスタンスで取り入れることが大切です。日々の食事内容などを振り返り、不足しがちな栄養素や成分をサプリメントで補いましょう。

監修してくれたのは…医師・後藤利夫さん
1988年、東京大学医学部卒業。独自の無麻酔・無痛大腸内視鏡検査法「水浸法」を開発。大腸内視鏡6万件以上無事故のベテラン医師。大腸がん予防から始まった腸内細菌や乳酸菌にも造詣が深く、菌のパワーを使って健康になる方法を各所で伝授し続けている乳酸菌の専門家。サプリメント「今日から腸活!」の監修も務める。
編集/根橋明日美 写真・イラスト/PIXTAほか

SKINCARE
PR

SKINCARE
PR

SKINCARE
PR

HEALTH
PR

SKINCARE
PR

SKINCARE
PR

SKINCARE
PR

SKINCARE
PR

SKINCARE
PR

HAIR
PR

2026年2月16日(月)23:59まで

2026年2月16日(月)23:59まで

2026年1月16日(金)23:59まで

2026年1月16日(金)23:59まで

2025年12月16日(火)23:59まで